御仏前の正しいお金の入れ方は?書き方・渡し方のマナーについても解説

四十九日以降の法要で香典を包む際、表書きに「御仏前」と記しますが、「御霊前」「御香典」という言葉もあるため、どれを記すべきか迷った経験はありませんか。
また、包むお金の書き方にもマナーがあり、間違えると失礼にあたります。
この記事では、「御仏前」「御霊前」「御香典」の違いから、お金の書き方や渡し方などのマナーについても解説します。
法要などのマナーは人に聞きづらいため、迷われている方の参考になれば幸いです。
御仏前とは

御仏前(ごぶつぜん)とは、四十九日法要以降の法要のお供え物や金封の表書きに記します。
仏教では亡くなった人は7日ごとに審判を受け、四十九日目に最後の審判が下されて成仏すると考えられています。
そのため、四十九日以前は「霊」として扱われ、四十九日以降は「仏」として供養されます。
この考えから、四十九日法要からは御仏前と記します。
御霊前・御香典との違い
御霊前と御香典の違いは、以下の通りです。
御霊前
御霊前(ごれいぜん)は、故人がまだ成仏していない、四十九日法要前に記す表書きです。
解説したように仏教の考えでは、四十九日前までは故人はまだ成仏していない「霊」として扱われるため、四十九日前の通夜・葬儀・初七日では「御霊前」と記します。
御香典
御香典(ごこうでん・おこうでん)は、通夜・葬儀・告別式など、故人を偲ぶ場で使われます。
宗派不明な場合の表書きは『御香典』と記します。
使い分けが必要な場合がある
仏教でも宗派によって死後の考え方が異なるため、「御霊前」と「御仏前」を使い分ける必要があります。
故人の宗派がわかるのであれば、その宗派に合わせて表書きを記しましょう。
宗派がわからない場合は「御香典」と記しましょう。
表書きは、故人への敬意を示す大切なものです。
失礼にならないよう注意し、故人の宗派に合わせて使い分けましょう。
御仏前の書き方
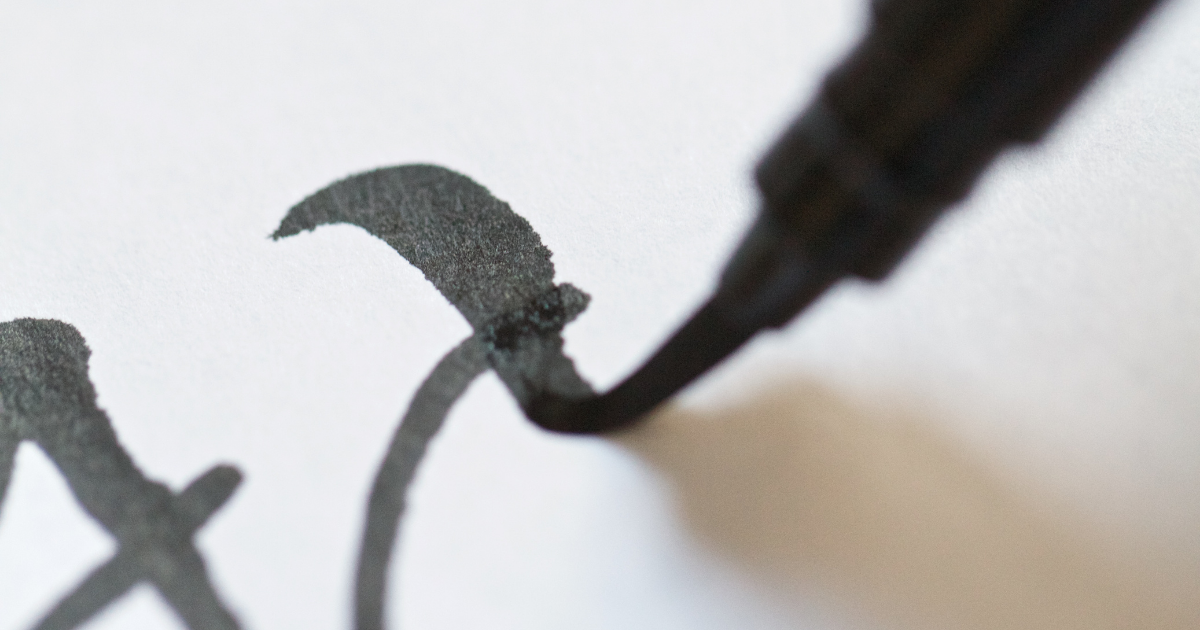
御仏前の書き方には、マナーがあります。
故人やご遺族に対して、失礼のないように書き方や筆記具の選び方を知っておきましょう。
表書き
不祝儀袋の表書きは、袋の中央上部に「御仏前」と記します。
格式を重んじる場合は、旧字体の「御佛前」と記しても問題ありません。
表書きが水引に重なってしまわないように、水引の位置を確認してから記入しましょう。
また、表書きの下に自分のフルネームを記入しますが、こちらも水引にかからないように注意してください。
表書きは、ご遺族が最初に目にする部分です。弔意が伝わるように丁寧に記しましょう。
連名の書き方
夫婦で参列する場合、中央に夫のフルネームを記入し、左隣に妻の名前のみ記します。
会社などの団体で参列する場合は、中央に上司のフルネームを記入し、左に他の人のフルネームを記入します。
4名以上の場合、中央に代表者のフルネームを記入して、左に「一同」または「他」と記すのが一般的な記入方法です。
中袋
不祝儀袋に中袋が付属している場合、表面中央に金額を旧字体の大字で記入します。
旧字体の書き方については、後ほど解説します。
裏面左側には、右から郵便番号・住所・氏名の順で縦書きで記入します。
これは、ご遺族が香典返しの準備に必要な情報となるため、マンションなどの建物名も省略せず、郵便番号や住所の番地は漢数字で記入しましょう。
中袋がない場合
不祝儀袋の中には、中袋が付属していない種類もあります。この場合、不祝儀袋の裏面左下に氏名などを記入します。
中袋がある場合と同じで、右から郵便番号・住所・氏名の順で記入し、その横に包んだ金額を記入します。
記入する項目が多いため、文字の大きさなどのバランスに注意して記入しましょう。
金額の書き方
金額は、旧字体の大字で記入します。
金額の前に「金」の文字を記し、5千円の場合は「金伍仟圓」、1万円は「金壱萬圓」、3万円なら「金参萬圓」と記載します。
なお、御仏前に包む金額には、「4」と「9」がつく金額は包みません。
この2つの数字は、それぞれ「死」と「苦」を連想させる忌み言葉とされており、避けるのがマナーです。
使用する筆記具
筆記具は、筆または筆ペンを使用します。
弔事では「薄墨」を使用すると思われるかもしれませんが、薄墨を使用するのは通夜や葬儀など、四十九日法要の前までです。
このため、四十九日法要以降に使われる御仏前には濃墨を使用します。
不祝儀袋の外袋は、筆または筆ペンで記入しましょう。
ただし、中袋に記載する氏名や住所などを筆や筆ペンで記入すると、文字数の多さから読みづらくなり、見栄えも良くありません。
外から見えない中袋は読みやすさを重視して、万年筆などで記入しても問題ありません。
御仏前のお金の入れ方とマナー

御仏前へのお金の入れ方、渡し方にもマナーがあります。
失礼にならないよう、お金の入れ方と渡し方のマナーを確認しましょう。
お金の入れ方は?
御仏前として包むお金は、不祝儀袋に入れます。
お金は肖像画を袋の裏面に向けて、下向きにそろえて入れます。
御仏前に入れるお金は、不祝儀袋についている中袋に入れるのが一般的ですが、「不幸が重なる」として、中袋にお金を入れることを敬遠する地域もあります。
このため、地域の慣習についても注意が必要です。
新札は使わない
御仏前として包むお札は、新札は避けましょう。
訃報の際、新札を入れるのは事前に準備していたかのような印象を相手に与えるため、失礼にあたるとされています。
新札しかない場合は、軽く折り目をつけてから入れましょう。
また、汚れたお札を入れることも失礼にあたります。
不祝儀袋に入れる前に汚れがないか確認しましょう。
御仏前は袱紗(ふくさ)に包む
御仏前は、袱紗と呼ばれる布に包んで持参します。
袱紗に包むのは金封が汚れたり、傷をつけたりしないようにするためです。
御仏前は法要前に袱紗から取り出し、施主に渡します。
御仏前は、施主から見て表面が読める向きにして両手を添えて渡します。
その際、「御仏前にお供えください」と一言、添えましょう。
御仏前に入れる金額の目安

御仏前には、どのくらいの金額を包むべきか悩む方も少なくないでしょう。
ここでは、法要の際の御仏前の金額の目安について解説します。
四十九日
四十九日法要は、故人が成仏するとされる重要な節目となる供養です。
この日を境に忌明けとなり、法要の参列者は多くなりやすく、精進落としとして食事が用意される場合もあります。
これらの理由から、法要に費用がかかりやすいため、御仏前は少し多めに包みましょう。
| 親兄弟 | 1万円~5万円 |
| 祖父母 | 1万円~3万円 |
| その他の親族 | 5千円~3万円 |
| 友人・知人 | 5千円~1万円 |
初盆
初盆は、故人が亡くなられて最初に迎えるお盆ということもあり、丁重に供養が行われます。
法要後に参列者と食事を取ったり、地域によっては故人が帰ってくるのに迷わないよう提灯を飾ったりする慣習もあります。
このため、四十九日法要と同じように少し多めに包みましょう。
| 親兄弟 | 1万円~3万円 |
| 祖父母 | 5千円~3万円 |
| その他の親族 | 5千円~1万円 |
| 友人・知人 | 3千円~1万円 |
一周忌・三回忌
一周忌や三回忌も、故人を偲ぶ節目となる法要です。
特に一周忌は1つの区切りとして考える方が多いため、できるだけ多くの親戚、友人・知人に参列を呼びかけて、大きな法要となる場合があります。
食事が用意されている場合は、それを踏まえて、少し多めに包みましょう。
三回忌の金額も一周忌と同じくらいと考えましょう。
| 親兄弟 | 1万円~5万円 |
| 祖父母 | 5千円~3万円 |
| その他の親族 | 5千円~1万円 |
| 友人・知人 | 3千円~1万円 |
金額が多すぎると失礼になる
御仏前として包む金額が多すぎると、「不幸が重なる」と不幸を連想させる恐れがあります。
これは「重なる」が、忌み言葉とされるためです。
故人に恩があり、ご遺族の助けになりたいという思いがあっても、御仏前の金額は目安となる金額に収まるようにしましょう。
また、金額以外の注意点として、「偶数」の金額は包まないように注意しましょう。
偶数は割り切れる数字として、故人との縁が切れることを連想させるためです。
御仏前でよくある質問

御仏前でよくある疑問について、回答します。
ご遺族から御仏前を辞退された場合は?
故人やご遺族の意思で、御仏前を辞退される場合があります。
御仏前を辞退する理由は、故人の意思や香典返しの手間を減らすなど、さまざまです。
このような場合、無理に御仏前を渡そうとするのは失礼になるため、故人やご遺族の意思を尊重するのが礼儀です。
弔意の気持ちを示したい場合は、供花やお供え物を手配するか、後日、弔電を送るなど、金銭以外の形で弔意を示しましょう。
御仏前は郵送できる?
仕事の都合や遠方に住んでいて法要に参列するのが難しい場合は、御仏前を郵送でお送りしても失礼にはなりません。
ただし、現金を普通郵便で郵送することは法律で禁じられているため、「現金書留」で郵送してください。
なお、現金書留は専用の封筒を郵便局で購入して、窓口で手続きをする必要があります。不祝儀袋を専用の封筒に入れて送るのが一般的です。
法要に参列できないことをお詫びする一言を添えて、郵送しましょう。
上司などの代理で御仏前を預かった場合は?
職場の上司などの代理として法要に参列し、御仏前を預かる場合は受付の方や施主に「〇〇の代理で参りました」と、一言添えて、御仏前を渡しましょう。
受付の芳名帳に記帳する際は、勤務先の住所と社名を記入し、上司のフルネームを記入します。
この上司の名前の左下に「代」と記入し、自分のフルネームを記入します。
これは、ご遺族が後日、芳名帳を確認しやすくするための配慮です。
まとめ

本記事では、御仏前の金額の目安、不祝儀袋の書き方、渡す際のマナーについて解説しました。
「御仏前」とは、四十九日後の法要の金封やお供え物の表書きに使われる言葉です。
四十九日前までの表書きに使われる「御霊前」と混同しないように、それぞれの言葉の意味と宗派による使い分けについても注意しましょう。
関内陵苑では、供養の流れや作法についても「お役立ちコラム」でご紹介しております。
葬儀や法要についても承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。


