四十九日のお供えへのお返し!のしの書き方や品物の選び方まで解説

四十九日の法要に際し、お供えや香典をいただくことがあります。
その際、感謝の気持ちを伝えるために用意するのがお返しの品物です。
しかし、品物選びやのしの書き方など、分からないことも多いのではないでしょうか。
本記事では、四十九日のお返しに関するマナーや考え方を解説します。
心のこもったお返しを準備するために、ぜひお役立てください。
四十九日のお返しのマナーや考え方

四十九日のお返しは、故人を偲んでくださった方々へ感謝を伝える大切な習慣です。
まずはお返しの基本的な考え方や、贈る時期、金額の相場といったマナーについて理解を深めましょう。
お供え・香典返し・引き出物の違い
お供えや香典返し、引き出物は混同されがちですが、それぞれ意味合いが異なります。
まず「お供えへのお返し」は、品物でお供えをいただいた方への返礼品です。
次に「香典返し」は、通夜や葬儀でいただいた香典(現金)に対するお返しを指します。
そして「引き出物」は、法要に参列してくださった方へ、お帰りの際に手渡すお礼の品です。
お返しが必要な場合と不要な場合
お返しは、香典やお供えをいただいたすべての方へ贈るのが基本です。
法要への参列の有無は関係ありません。
一方で、お返しが不要な場合もあります。
例えば、香典をくださった方が「お返しはご辞退します」と意思表示された場合や、会社の福利厚生など規定でお返しを受け取れない場合です。
お返しを渡す時期
お返しを渡す時期は四十九日の法要を終え、忌明け(きあけ)を迎えてからです。
これは、滞りなく法要が済み、故人の供養の一区切りがついたことを報告する意味も含まれています。
具体的には、法要後から1ヵ月以内を目安に、相手の手元に届くように手配するのがマナーです。
最近では、葬儀当日にお返しをお渡しする「当日返し」という方法もありますが、これはあくまでも葬儀に対するもので、四十九日法要のお返しとは区別して考えましょう。
四十九日香典返しの金額相場
お返しの金額は、いただいた香典やお供えの金額に応じて決めるのが一般的です。
基本的には「半返し」といって、いただいた金額の半額程度の品物を選ぶのが主流です。
ただし、地域や関係性によっては3分の1程度の金額でも失礼にはあたりません。
例えば、1万円の香典をいただいた場合は、3,000円から5,000円程度の品物をお返しとして準備すると良いでしょう。
四十九日のお供えのお返しを選ぶポイント

お返しの品物選びは、感謝の気持ちを形にするうえで非常に重要です。
相手に負担をかけず、喜んで受け取ってもらえる品物を選ぶためのポイントを、具体的な例とともに解説します。
定番や人気の品物から選ぶ
お返しの品物選びで迷った際は、定番や人気の品から選ぶのが間違いのない方法です。
弔事のお返しでは使ったり食べたりするとなくなる品物が良いとされています。
これらは、「消えもの」と呼ばれます。
これは「悲しみを後に残さない」という意味が込められているからです。
具体的には、お茶やコーヒー、海苔、お菓子といった食品や、石鹸、洗剤などの日用品がよく選ばれます。
また、タオルは「悲しみを拭い去る」という意味で、定番の品物として人気があります。
受け取る方に喜ばれる実用的な品を選ぶ
定番も良いですが、相手の好みや家族構成を考えて品物を選ぶと、より一層気持ちが伝わります。
例えば、甘いものがお好きな方には有名店の焼き菓子を、お料理をされる方には調味料のセットを贈るのも良いでしょう。
相手の好みが分からない場合や、どなたにでも喜んでもらいたい場合は、カタログギフトが便利です。
受け取った方が好きなものを選べるため、近年では香典返しとして利用されることが増えています。
地域の風習や相場に合わせる
お返しの品物や習慣には、地域性が表れることがあります。
例えば、特定の地域ではお茶を贈るのが昔からの慣習であったり、品物に商品券を添えるのが一般的であったりします。
ご自身の地域の風習が分からない場合は、年長の親族や地域のギフト専門店、葬儀社などに相談してみると良いでしょう。
地域の慣習に合わせることで、相手に対してより丁寧な印象を与えることができます。
日持ちや保存性を考慮する
食品をお返しに選ぶ場合は、日持ちや保存性を十分に考慮することが大切です。
受け取った方がすぐに消費しなければならない生菓子などは、かえって相手の負担になる可能性があります。
少なくとも1ヵ月以上は日持ちする焼き菓子や乾物、缶詰などを選ぶのが無難でしょう。
また、個包装になっているお菓子などは、ご家族で分けやすく、好きなタイミングで食べられるため喜ばれる傾向にあります。
高額なお供え・香典をいただいた場合の対応も検討する
親族などから5万円、10万円といった高額の香典やお供えをいただくことがあります。
この場合は、ご遺族への援助や支援の気持ちが強く込められているため、必ずしも半返しにする必要はありません。
いただいた香典の金額の3分の1から4分の1程度(1万円以上を目安)の品物をお返しし、感謝の気持ちを丁寧に綴ったお礼状を添えましょう。
品物選びに迷う場合は、上質な品物が揃っているカタログギフトを選ぶのも方法の一つです。
四十九日のお返しの「のし」の書き方
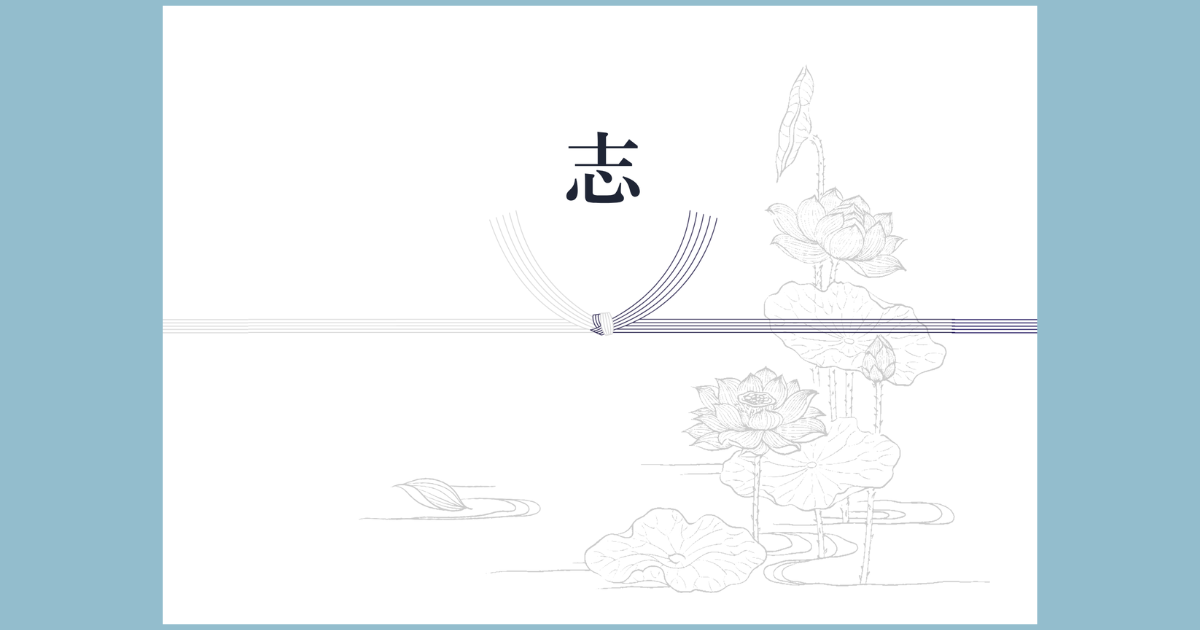
お返しの品物には、「のし(掛け紙)」を掛けます。
のしには、誰からどのような目的で贈るのかを示す大切な役割があります。
ここでは、表書きや水引の選び方など、のしの基本的な書き方とマナーを解説します。
表書きの基本は「志」や「満中陰志」
のしの上段に書く言葉を「表書き」と言います。
四十九日のお返しで最も一般的に使われるのが「志(こころざし)」です。
これは宗教や宗派を問わず、全国的に使用できる一般的な言葉で、「感謝の気持ちです」といった意味合いを持ちます。
また、関西地方など西日本では「満中陰志(まんちゅういんし)」という表書きもよく用いられます。
これは、「四十九日の満中陰を無事に終えました」という報告を兼ねた言葉です。
贈り主の名前の書き方と表記の注意点
のしの下段には、贈り主の名前を書きます。
一般的には、喪家の姓のみを「〇〇家」と記すか、喪主のフルネームを書きます。
連名にする場合は、3名までなら全員の名前を書き、それ以上の人数の場合は「〇〇家 親族一同」などとまとめます。
名前を書く際は、通夜や葬儀の香典袋とは異なり、濃い墨の筆か筆ペンを使用します。
薄墨は悲しみの涙を表すもので、忌明け後のお返しには使いません。
水引の選び方
弔事用のお返しに用いる水引は、「結び切り」という一度結んだらほどけない結び方のものを選びます。
これは「不幸を繰り返さない」という意味が込められています。
色は、黒白の結び切りを用いることが全国的に最も一般的です。
ただし、関西から西日本の地域では、黄白の結び切りが使われることもあります。
地域の慣習が分からない場合は、黒白の水引を選んでおきましょう。
また、品物を購入するギフト店などで相談するのも良いでしょう。
四十九日のお返しの渡し方

お返しの品を準備したら、適切な方法で相手にお渡しします。
法要当日に手渡す場合と、後日郵送する場合のそれぞれの注意点や特別な相手への渡し方について解説します。
当日か郵送
お返しの渡し方には、大きく分けて二つの方法があります。
一つは四十九日の法要当日に、参列してくださった方へ直接手渡す方法です。
この場合、引き出物と兼ねる形になります。
もう一つは、法要を終えた後、忌明けの報告を兼ねて郵送する方法です。
法要に参列されなかった方や、遠方にお住まいの方へはこちらの方法で贈ります。
どちらの方法でもマナー違反にはなりませんが、近年では後日郵送するケースも増えています。
郵送の場合の注意点
郵送する場合は、お礼状(挨拶状)を品物に添えるのがマナーです。
お礼状には、香典やお供えをいただいたことへの感謝、無事に四十九日法要を終えたことの報告、そしてお返しの品を送る旨を記します。
また、葬儀当日に香典返し(当日返し)をしている方に、誤って再度お返しを送らないよう注意が必要です。
誰にいつお返しをしたか、リストを作成して管理すると間違いを防ぐことができます。
親族への香典返しの注意点
親族、特に両親や兄弟など近しい間柄の方へのお返しは、少し配慮が必要です。
先述のとおり、高額の香典には、ご遺族の今後の生活を支えたいという強い気持ちが込められています。
このため、律儀に半返しをすると、かえって相手を恐縮させてしまうことがあります。
この場合は、ご厚意に甘えてその分、心のこもったお礼状で深い感謝の意を伝えるのが良いでしょう。
まとめ

四十九日のお返しは、故人を偲んでくださった方々への感謝を伝えるための大切な礼儀です。
半返しから3分の1返しを目安に、消えものなどの品物を選び、正しいのしを掛けてお贈りします。
マナーを守り、心を込めて対応することで、相手との良好な関係を保ち、故人の供養の一区切りを気持ちよく迎えることができるでしょう。
なお、関内陵苑では天候を気にせずお参りできる永代供養の納骨堂をご案内しております。
将来にわたるご供養のことでお悩みでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。


