終活はいつから始める?20代や40代・50代、おひとりさまに分けて解説

「終活」という言葉を聞いて、まだ自分には早いと感じる方もいることでしょう。
しかし、終活は単なる「死への準備」ではなく、これからの人生をより豊かに、安心して生きるための活動です。
本記事では、終活の本当の意味から、年代別や状況別に最適な始めるタイミング、具体的な進め方まで解説します。
終活とは?

終活とは、人生の終わりを見据えて、身の回りの整理や将来の準備を行う活動全般を指します。
漠然とした不安を解消し、残りの人生を自分らしく、前向きに過ごすことを目的としています。
家族への負担を減らすという側面もありますが、基本的には自分自身のためのポジティブな活動と捉えましょう。
終活はなんの略?
終活は「人生の終わりのための活動」を略した造語です。
2009年頃からメディアで使われるようになり、核家族化や高齢化といった社会背景の変化と共に広く浸透しました。
当初は少しネガティブな響きに聞こえたかもしれませんが、現在では、より良い人生を送るための準備として、幅広い世代に関心を持たれるようになっています。
自分の人生を総括し、未来に備えることで、今をより大切に生きるきっかけを与えてくれる活動です。
いつからでも始められるが「元気なうち」が理想
終活を始めるのに「早すぎる」ということはありません。
思い立ったその時が、あなたにとっての最適な始めどきです。
しかし、理想的なタイミングは、心身ともに健康で、判断力がしっかりしている「元気なうち」に始めることです。
終活では、財産の整理や医療・介護の意思決定など、冷静な判断が求められる重要な項目が多く含まれます。
また、物の片付けなど、体力が必要な作業も少なくありません。
気力や体力が充実しているうちに始めることで、焦らずに、そして着実に準備を進めることができ、より納得のいく終活につながります。
終活を始めるきっかけは?
人々が終活を意識するきっかけはさまざまです。
例えば、定年退職や子どもの独立といった、ライフステージの大きな変化が挙げられます。
また、親の介護や看取りを経験し、「自分の時は家族の負担を軽減したい」と感じて始める方も多いです。
還暦や古希などの節目の誕生日、親しい友人や知人の逝去、あるいはご自身の病気や入院をきっかけに、人生の終わりについて真剣に考え始めるケースもあるでしょう。
これらの出来事は、自身の人生を振り返り、これからを考える良い機会です。
年代別に見る終活の始めどき

終活で取り組むべき内容は、年代によって少しずつ異なります。
ここでは、20代から60代以降まで、それぞれの年代における終活のポイントと始めどきについて解説します。
20代・30代の終活
この年代の終活は、いわば「人生設計(ライフプランニング)」そのものと捉えるのが良いでしょう。
将来の夢や目標を明確にし、それに向かって計画的に準備を進めることが中心となります。
まずは、万が一の事態に備えて、生命保険や医療保険の内容がご自身の現状に合っているかを見直すことが大切です。
また、将来を見据えた資産形成(NISAやiDeCoなど)を始めるのにも最適な時期といえます。
さらに、スマートフォンやSNSアカウントといった「デジタル遺品」の整理も、若いうちから意識すべき重要な終活の一つです。
パスワードなどをリスト化し、信頼できる人にだけ共有方法を伝えておくだけでも、いざというときに役立ちます。
40代・50代の終活
40代・50代は、子育てや仕事で多忙な時期ですが、親の高齢化やご自身の健康を意識し始め、老後が現実的な視野に入ってくる年代です。
この時期の終活は、これまでの人生の棚卸しと、老後への具体的な準備がテーマです。
体力があるうちに、家の中の本格的な身辺整理(断捨離)を始めることをおすすめします。
これは、単に物を減らすだけでなく、自分にとって遺したいものを見極める作業でもあります。
また、住宅ローンの見直しや、退職金・年金を踏まえた老後資金のシミュレーション、親の介護や相続について家族と話し合うことも、この時期に始めておきたい重要な終活です。
60代以降の終活
60代は、多くの方が定年退職を迎え、時間的にも精神的にも余裕が生まれるため、終活を本格的に始めるのに最適な時期です。
そこで、退職後のセカンドライフをどう過ごすか、趣味や社会貢献活動など具体的なライフスタイルを設計しましょう。
そして、医療や介護に関するご自身の希望を明確にし、リビングウィル(尊厳死の宣言書)やエンディングノートに具体的に記しておくことが大切です。
さらに、ご自身の葬儀やお墓についても、具体的な準備を始める段階に入ります。
葬儀社の選定や費用の準備、お墓はどのように承継していくのか、あるいは納骨堂のような新しい形を選ぶのか、家族と話し合いながら決めていきましょう。
おひとりさまの終活

配偶者や子どもがいない「おひとりさま」にとって、終活はご自身の未来を守るために特に重要です。
事前の準備がご自身の安心に直結します。
おひとりさまの課題
おひとりさまの終活における最大の課題は、ご自身が病気や認知症で判断能力が低下した際の「医療・介護」と、亡くなった後の「死後事務」です。
延命治療の希望など、医療に関する意思表示を公正証書などで法的に有効な形で残しておくことが重要です。
また、入院時の身元保証や亡くなった後の各種手続きを誰に託すのかも決めておかなければなりません。
信頼できる友人や専門家と、「身元保証サービス」や「死後事務委任契約」を結んでおくことも検討しておきましょう。
終活における身辺整理
万が一の際、遠縁の親族や友人に過度な負担をかけないためにも、身辺整理は計画的に進めましょう。
持ち物の整理はもちろん、SNSアカウントやネット銀行などのデジタル資産の整理も重要です。
IDやパスワード、解約方法などを一覧にして、信頼できる人にだけその保管場所を伝えておくと、残された方がスムーズに手続きを進められます。
また、ご自身の財産を希望通りに遺すため、法的に有効な遺言書も作成しておきましょう。
終活を始める流れ
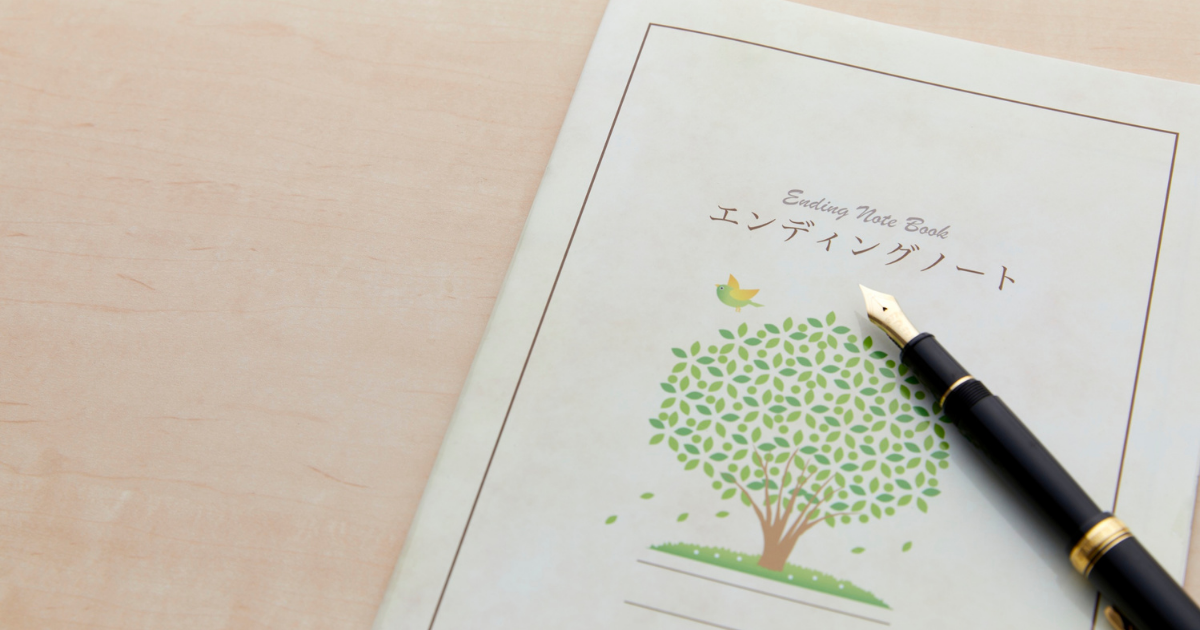
終活は、やるべきことが多岐にわたるため、何から手をつければ良いか迷ってしまうかもしれません。
ここでは、終活をスムーズに進めるための基本的な流れと、それぞれのステップでやるべきことを解説します。
何から始める?
終活の第一歩として、まずは「エンディングノート」を書くことから始めてみましょう。
これが、ご自身の考えを整理し、全体像を掴むための土台となります。
エンディングノートを書く
エンディングノートとは、ご自身の情報や希望、家族へのメッセージなどを自由に書き記すノートです。
法的効力はありませんが、自分の考えを整理し、家族に想いを伝えるためのツールです。
自分史、資産リスト、大切な人への連絡先、延命治療の希望、葬儀の要望など、市販のノートにはさまざまな項目があります。
まずは書けるところから埋めていくことで、やるべきことが明確になります。
医療・介護の希望をまとめる
エンディングノートと並行して、ご自身の医療・介護に関する希望を具体的にまとめておきましょう。
「どこで」「どのような」介護を受けたいか、延命治療は望むのか、といった意思表示は、ご家族が将来、難しい決断を迫られた際の大きな助けとなります。
まとめた内容は、家族や信頼できる人に伝えておき、その意思を託せる代理人を決めておくとより安心です。
資産・保険・契約情報を整理する
次にご自身の財産や契約関係をリストアップし、誰が見ても分かるように整理します。
預貯金、不動産、有価証券といったプラスの資産だけでなく、ローンなどのマイナスの資産もすべて洗い出しましょう。
また、加入している生命保険や医療保険、年金、利用しているサブスクリプションサービスなどの契約情報も一覧にしておくと、後の手続きがスムーズに進みます。
葬儀・お墓・供養方法の希望を考える
最後にご自身のエンディングについて具体的に考えます。
どのような規模や形式の葬儀を望むのか、誰に参列してほしいのか、といった希望をまとめましょう。
また、お墓をどうするのかも重要なテーマです。
伝統的なお墓を承継するのか、あるいは永代供養の納骨堂や樹木葬といった新しい供養の形を選ぶのか、ご自身の価値観や家族の状況に合わせて検討し、その費用も含めて希望を伝えておくことが大切です。
まとめ

終活は、どの年代から始めても早すぎることはありません。
元気なうちから始めることで、ご自身の人生を見つめ直し、これからの時間をより豊かに生きるための道しるべとなります。
まずはエンディングノートを手に取り、ご自身の想いを書き出すことから始めてみましょう。
終活の一環としてご自身の眠る場所をお考えの際には、関内陵苑もご検討ください。
当苑では宗教や宗派に関係なく、機械式納骨堂をご利用になれます。
納骨堂を検討している際は、ぜひお気軽にご相談ください。


